収益物件の減価償却とは?で節税効果を最大化する方法

収益物件における減価償却は、建物や設備の価値が年々減少する分を経費として計上し、税負担を軽減できる仕組みです。土地は対象外ですが、建物や設備の減価償却を正しく行うことで、収益を圧縮し節税につながります。
物件購入時に一度に全額を経費に計上するのではなく、法定耐用年数に基づいて分割計上するため、毎年の利益を調整しながら節税効果を得られます。主な計算方法には定額法や定率法があり、投資の戦略に応じた方法を選ぶことが大切です。
目次
収益物件の減価償却とは?

建物や設備の価値は年々減少していきますが、その減少分を経費として計上できるのが「減価償却」です。このプロセスをうまく活用することで、実際の支出を伴わずに税負担を軽減し、収益を最大化することが可能です。
◇減価償却とは
減価償却とは、一定の期間にわたって使用する資産の購入費用を、その使用期間に応じて分割して経費として計上する手法です。
例えば、収益物件を購入した場合、その物件の建物部分の購入費用を一度に計上するのではなく、法定耐用年数に基づいて分割して経費化します。これにより、毎年の利益を適切に調整し、税負担を軽減できるのが減価償却のメリットです。
収益物件の減価償却を利用することで、実際には支出を伴わない経費を計上することができ、結果的に利益を圧縮して節税効果を得ることが可能です。
不動産投資においては、建物や設備の価値が減少することを考慮し、減価償却を通じて資産の価値減少を経費化するため、長期的な資産運用にも有利に働きます。
◇土地は対象とならない
減価償却の対象となるのは、主に建物や設備であり、土地はその対象外です。その理由は、土地は基本的に経年による価値の減少がないためです。
例えば、アパートを購入した場合、その土地部分の価値は減価償却できない一方で、建物部分の価値は耐用年数に基づき分割して経費として計上できます。
減価償却を考慮する際には、物件購入時に建物と土地の価格を適切に分けておくことが重要です。土地価格と建物価格が混同されると、後々の減価償却計算が複雑になるだけでなく、適切な節税効果を得られない可能性があります。
したがって、購入時に不動産業者や税理士と相談し、正確な価格内訳を設定することが大切です。
【あわせて読みたい】
定額法と定率法~減価償却の計算方法

減価償却を正しく活用するためには、その計算方法を理解することが不可欠です。不動産の減価償却には、主に「定額法」と「定率法」という2つの方法があり、それぞれの特性に応じた使い方が求められます。
◇定額法
定額法は、減価償却費を毎年一定額ずつ計上する方法です。この方法では、物件の購入価格を法定耐用年数で割り、毎年同じ額を経費として計上します。
例えば、購入した収益物件の取得価額が5,000万円で、法定耐用年数が20年の場合、毎年250万円ずつ減価償却費として計上できます。
定額法は非常にシンプルで、毎年の計上額が変わらないため、将来の経費計画が立てやすいという特徴があります。特に長期的に安定した収益を見込む物件に適しており、計算の手間も少ないことから初心者にも採用しやすい方法です。
また、減価償却費が毎年一定であるため、税金の負担が大きく変動することもなく、安定したキャッシュフローを維持するのに向いています。
しかし一方で、物件を早期に売却する予定がある場合には、減価償却の初期に大きな節税効果が得られないため、他の方法を検討する必要があるでしょう。
◇定率法
定率法は、毎年一定の割合で計上額が減少していく方法です。この方法では、初年度に最も多くの減価償却費を計上し、年を追うごとにその額が少なくなります。
例えば、取得価額が5,000万円で、法定耐用年数が20年の場合、初年度に大きな額を償却し、翌年以降は残高に対して計算されるため、少しずつ減っていきます。
定率法は初期に多くの経費を計上できるため、短期的な節税効果を狙いたい場合に有効です。特に、収益物件を早期に売却する可能性がある場合や、最初の数年でキャッシュフローの改善を図りたい場合に適しています。初期の減価償却費が大きくなるため、早期の節税効果が期待できます。
しかし、年数が進むにつれて減価償却費が少なくなるため、長期的な視点で見ると安定性に欠ける場合があります。
【あわせて読みたい】
減価償却が終了したら売却する手も

減価償却が終了したタイミングは、収益物件の売却を検討する好機とされています。減価償却が終わると、経費として計上できる額が減少し、税負担が増えることでキャッシュフローに影響が出る可能性があります。
そのため、税金対策や資産運用の観点からも、このタイミングで売却を行い、得た資金を新たな投資に活用することが戦略的な選択となります。
◇売却
減価償却が終了した物件は、売却を検討する好機と言えます。減価償却期間が終わると、利益が増加するため納税額が増え、キャッシュフローが悪化する可能性があります。このような状況を回避するために、収益物件の売却は効果的な方法です。
売却を行う際には、売却益に対して譲渡税が課されることも念頭に置いて計画を立てる必要があります。特に、売却価格と簿価の差額が大きい場合には譲渡税の負担が増えるため、タイミングを見極めることが重要です。
また、売却することで得た資金を次の投資に充てることができ、新たな収益物件を購入することで、再び減価償却を活用して節税を図ることも可能です。
◇更地にする
老朽化が進んだ物件や、立地条件が良く土地としての需要が高い場合、建物を取り壊して更地にする選択肢もあります。更地にすることで、土地としての活用価値が上がり、売却価格も向上する可能性があります。
特に、再開発エリアや商業施設が近隣にある場合、土地の需要が高まりやすく、より高値での売却が期待できるでしょう。
ただし、更地にするには建物の解体費用がかかるため、事前に費用対効果をしっかりと検討する必要があります。また、入居者がいる場合には立ち退き交渉も必要となり、時間と労力がかかる点にも注意が必要です。
更地にして土地として売却することで、より高い収益を見込むことができる反面、準備と資金の調達に時間がかかる場合もあるため、計画的に進めることが重要です。
◇建て替える
長期的にその土地で収益を上げ続けたい場合、物件の建て替えも有効な選択肢です。特に、好立地の物件であれば、建物を新築することで、再び減価償却を開始できるため、税制上のメリットも増大します。
また、最新の建築技術やデザインを取り入れることで、入居率の向上や家賃の増加も期待できるでしょう。
ただし、建て替えの際には、新たにローンを組むことや、立ち退き費用が発生する可能性があります。また、建て替えを検討する際には、地元の建築規制や建物の構造に関する法律を確認し、適切な建築計画を立てることが不可欠です。
さらに、建て替え後の入居者募集や管理計画も重要な要素となるため、総合的な戦略を持って進めましょう。
【あわせて読みたい】
▼一棟マンションが収益物件として人気上昇中!一棟マンションを高額売却するコツ
収益物件の減価償却で上手に節税

収益物件の建物部分に対する減価償却を活用することで、支出を伴わずに経費を計上し、課税対象額を圧縮できます。この節税効果を最大限に活用することで、安定したキャッシュフローを維持しながら、長期的な利益確保が可能になります。
◇経費になる
減価償却の最大の魅力は、実際の支出を伴わずに経費として計上できる点です。収益物件の建物部分は、時間の経過とともに価値が下がるため、その減少分を経費として処理できます。これにより、毎年の収入に対する課税対象額が減少し、納税額も軽減されます。
例えば、年間家賃収入が1,000万円あった場合、減価償却費として200万円を計上できれば、課税対象は800万円になります。支出が発生していないにもかかわらず、経費として計上できるため、実質的な利益を圧縮できるのです。
また、減価償却を経費として計上できる期間は長く、収益物件を保有している限り、その節税メリットを享受し続けられます。
建物の法定耐用年数に基づいて毎年定額、または定率で経費計上が可能です。これにより、長期的な税金対策ができるため、安定したキャッシュフローを確保しやすくなります。
◇節税できる
収益物件を法人で保有している場合、減価償却によって計上された経費により、法人の利益が減少します。法人税は利益に対して課税されるため、減価償却費を経費として計上することで、法人税額を抑えることが可能です。
例えば、年間利益が500万円の場合、減価償却で100万円を経費計上できれば、利益が400万円に圧縮され、その分の税額が軽減されます。
また、不動産所得が個人の場合でも、減価償却は非常に有効です。不動産所得が赤字になった場合、他の所得(例えば給与所得)と損益通算することができ、結果として全体の課税所得を減らすことが可能です。これにより、個人の所得税や住民税の負担を軽減することができます。
特に給与所得の高い個人にとっては、減価償却をうまく活用することで、税金の支払いを大幅に減らせるため、不動産投資を行う際の重要な節税手段となるでしょう。
【あわせて読みたい】
減価償却を効果的に活用する方法
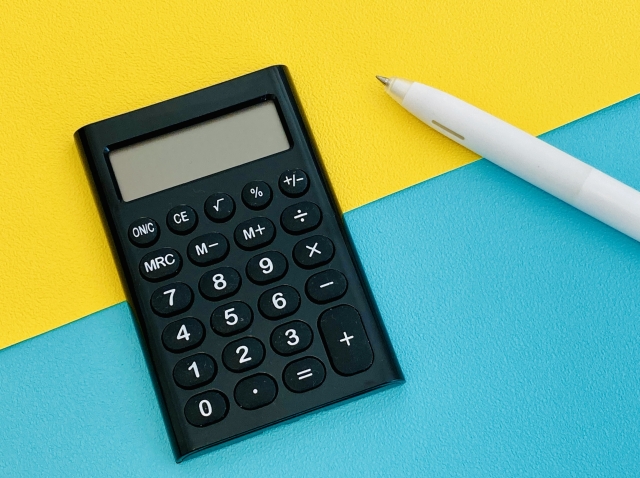
減価償却は、不動産投資において税負担を軽減するための有力な手段です。適切に活用することで、毎年の所得税を抑え、キャッシュフローの改善にもつながります。
◇築年数の古い木造物件への投資
木造物件の法定耐用年数は22年とされており、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造に比べて短いのが特徴です。そのため、同じ価格の物件であっても、木造のほうが1年あたりに計上できる減価償却費が多くなり、結果として課税対象となる所得を抑えやすくなります。特に築年数が法定耐用年数を超えた物件であれば、償却期間が4年に短縮されるため、減価償却費をさらに多く計上でき、税負担の軽減につながるでしょう。また、築古の木造物件は比較的価格が抑えられていることが多く、初期投資を抑えながら減価償却のメリットを活かしやすい点も魅力です。ただし、修繕費や維持管理のコストがかかる可能性もあるため、長期的な収支バランスを見極めることが大切です。減価償却を効果的に活用したい場合、築古の木造物件への投資は有力な選択肢の一つと言えるでしょう
◇所得が高いほど減価償却による節税効果が大きい
不動産所得は総合課税制度の対象となるため、給与所得や事業所得と合算して所得税が計算されます。所得税は累進課税制度に基づいており、所得が増えるほど税率も高くなる仕組みです。そのため、減価償却を活用して不動産所得を抑えることで、所得が高い人ほど大きな節税効果を得られるのが特徴です。
たとえば、課税所得が500万円の人と1,000万円の人が、それぞれ50万円の減価償却を計上した場合、適用される税率によって節税額が異なります。500万円の人の税率は20%で、税負担の軽減額は約10万円です。一方、1,000万円の人は税率33%のため、節税額は約16.5万円となり、所得が高いほど減価償却による節税効果が大きくなることが分かります。
このように、所得税の負担が大きい人ほど、減価償却を活用することで税負担を効果的に軽減できます。高所得者が不動産投資を行う際は、減価償却をうまく取り入れることで、手元に残る資金を増やし、資産形成を効率的に進めることが可能です。
◇不動産を売却する際は、所有期間が5年以上経過してから
投資用不動産を売却する際は、所有期間が5年を超えてからの売却が有利です。不動産の売却によって得た譲渡所得には、譲渡所得税と住民税がかかりますが、その税率は所有期間によって大きく変わります。5年以内に売却すると短期譲渡所得として扱われ、約39.63%の税率が適用されます。一方、5年を超えて売却した場合は長期譲渡所得となり、税率が約20.315%に下がるため、税負担を大幅に抑えることが可能です。
例えば、同じ価格で売却した場合でも、短期譲渡所得の税率では利益の約40%が税金として差し引かれますが、長期譲渡所得なら約20%の負担ですみます。そのため、所有期間が5年を超えてから売却することで、手元に残る利益が増えるというメリットがあります。
また、譲渡所得税は給与所得や事業所得とは別に計算されるため、所得全体の税負担を考慮しながら売却時期を決めることも重要です。不動産投資でより多くの利益を確保するためにも、できる限り5年を超えてから売却することを検討するとよいでしょう。
【あわせて読みたい】
収益物件における減価償却の落とし穴

収益物件に投資する際、減価償却を効果的に活用することで税負担を軽減できますが、一方で注意すべき落とし穴もあります。減価償却の効果とリスクをしっかりと理解し、計画的に運用することが成功へのポイントとなります。
◇新築区分マンションは節税効果が得にくい
新築区分マンションは、法定耐用年数が47年と長いため、減価償却費が少なくなりがちです。初年度には登記費用や融資手数料などの経費を計上できるため、赤字が出やすく、その結果税負担を軽減できる場合もあります。しかし、2年目以降は帳簿上の利益が増え、納税額が逆に増加することがあります。また、新築区分マンションは価格が割高で利回りが低いことが多く、長期的な投資としてはリスクが伴うケースも多いです。そのため投資を検討する際には、利回りだけでなく、将来的な税負担や物件の維持管理費用なども十分に考慮し、全体的な収益性を見極めましょう。
◇出口戦略を誤ると重大な損失を被ることがある
不動産投資における出口戦略は、最終的に物件をどのように処分するかを決定する重要なポイントです。減価償却を活用して税負担を軽減し、安定した収益を得ることができたとしても、出口戦略を誤ると予想以上の損失を生む可能性があります。不動産投資の目的は、税負担を減らすことだけでなく、安定した収益を得ることです。したがって、投資後は出口戦略を意識して物件選びを行うことが重要です。適切な出口戦略を選ばないと、最終的に大きな損失を被ることになるかもしれません。
【あわせて読みたい】
▼収益物件を売却したほうがよいタイミングは?売り時の見極め方を解説
北海道でおすすめの不動産会社3選
不動産の取引は人生の大きな決断の一つであり、スムーズかつ納得のいく取引を実現するためには、地域に精通し、実績のある会社を選ぶことが大切です。適切な不動産会社と出会うことが、成功する取引への第一歩と言えるでしょう。
◇スペースエンタープライズ株式会社

引用元:スペースエンタープライズ株式会社
スペースエンタープライズ株式会社は、札幌市やその近郊、江別市での収益物件の売却に特化した不動産会社です。「早く」「高く」売却するための戦略を強みとし、常に顧客の利益を最優先に考えた提案を行っています。不動産の売買・賃貸・管理に精通したスタッフが多数在籍しており、最適な売却プランを提案できるのも特徴です。
| 会社名 | スペースエンタープライズ株式会社 札幌支店 |
| 所在地 | 〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東13-26-45 |
| 電話番号 | 011-522-9540 |
| 公式ホームページ | https://space-enterprise.jp/ |
また、物件の価値を最大限に引き出す出口戦略にも強みがあり、市場の動向を踏まえた適切な売却サポートを提供しています。スピーディーな売却と利益の最大化を両立させる戦略が魅力の企業です。
スペースエンタープライズ株式会社について詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。
▼利益最大化とスピード現金化を実現!収益物件売買におけるスペースエンタープライズの秘策
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼スペースエンタープライズ株式会社の公式ホームページはこちら
◇株式会社サンコーポレーション

株式会社サンコーポレーションは、不動産売買だけでなく、不動産管理のスペシャリストとしても高い評価を受けている会社です。物件を多角的に分析し、その結果をもとに最適な提案を行うことで、不動産投資の成功をサポートしています。そして運用の過程で発生するさまざまな課題に対しても、豊富な市場知識を活かして調査を行い、迅速かつ的確な改善策を提案できる体制を整えています。
| 会社名 | 株式会社サンコーポレーション |
| 所在地 | 〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西4-2-26 北晴北16ビル 2F |
| 電話番号 | 011-717-4311 |
| 公式ホームページ | https://sun-kanri.info/ |
サンコーポレーションでは、厳しい社内基準をクリアした経験豊富なスタッフのみがオーナーの担当を務め、的確なアドバイスを提供することが可能です。オーナーと共に歩みながら、資産価値の向上を目指す姿勢が強みです。
札幌市・江別市・北広島市・千歳市の収益物件売却|おすすめ不動産会社3選
◇東急リバブル(新さっぽろセンター)

東急リバブルは、設立51年の実績を持ち、全国に223店舗の売買仲介ネットワークを展開する不動産流通会社です。北海道では『新さっぽろセンター』を拠点とし、札幌市厚別区・清田区・恵庭市・江別市・北広島市・千歳市エリアの売却・購入相談に対応しています。新さっぽろ駅前再開発により誕生した商業施設『BiVi 新さっぽろ』内にあり、アクセスの良さも魅力です。
| 会社名 | 東急リバブル(新さっぽろセンター) |
| 所在地 | 〒004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央一条6-3-3 BiVi新さっぽろ 3F |
| 電話番号 | 0800-111-0983 |
| 公式ホームページ | https://www.livable.co.jp/branch/shinsapporo/ |
不動産相続、住み替え、売却や購入など、さまざまな悩みに応じた柔軟なサポートを提供し、マンション・一戸建て・土地・アパート・収益不動産など幅広い不動産取引に対応しています。相続税対策や空き家対策、投資相談にも力を入れ、短期的な売却から中長期的な資産運用まで相談ができます。
札幌市・江別市・北広島市・千歳市の収益物件売却|おすすめ不動産会社3選
収益物件における減価償却とは、建物や設備の価値が年々減少する分を経費として計上し、その分を活用して税負担を軽減できる制度です。
物件購入時に購入費用を一度に経費計上するのではなく、法定耐用年数に基づいて分割し、毎年の経費として計上することで、利益の調整が可能となり、税金を抑える効果があります。
特に、不動産投資では、この減価償却を利用して実際の支出がなくても利益を圧縮し、節税が可能です。例えば、建物部分の費用を分割して計上することで、長期的に渡って税金を抑え、収益を最大化できます。
一方、土地は価値が減少しないため減価償却の対象外となりますが、建物や設備はその価値が時間とともに減少するため、その分を経費化することが重要です。
減価償却の計算には「定額法」と「定率法」があり、定額法は毎年同じ額を経費として計上し、安定したキャッシュフローを維持できるため、長期的に運用する物件に適しています。一方、定率法は初期に多くの経費を計上し、早期の節税効果を狙う場合に有効です。
関連する記事

利益最大化とスピード現金化を実現!収益物件売買におけるスペー...
スペースエンタープライズは、顧客のニーズに応じた即日買取査定とじっくり売却高額査定の2つの査定方法を提供しています。即日買取は迅速な現金化に適し、じっ...
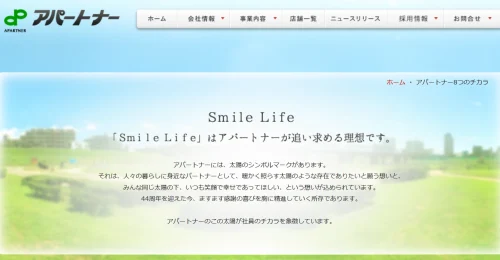
収益物件売却のプロが徹底サポート!株式会社アパートナー札幌支...
株式会社アパートナー札幌支店は、不動産売買や賃貸管理を通じてオーナーの利益最大化を支援する企業です。収益物件の売却や経営代行に強みがあり、地域貢献活動...

